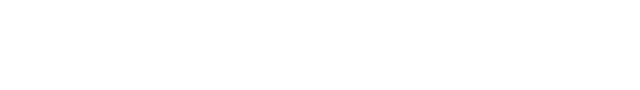息切れ・むくみ…それ、心臓の疲れかもしれません ― 心不全 New.2025/9
最近、ちょっと動くだけで息切れ?
足のむくみや体重の増加、年のせいと思っていませんか?
実はそれ、心不全のサインかもしれません。
自覚症状がないまま進行しているケースもあります。
最近、体力が落ちたなぁ。
感染症の流行でステイホーム生活になり、それ以後、運動をやめてしまった。
また始めなきゃ…そう思っていたけれど――
それ以上に、階段を上るだけで息切れがする。
夕方になると足がむくんで靴が履きにくくなるし、靴下のゴムの跡もくっきり残る。
夜、横になると苦しくて目が覚めることもある。
体重も、気づけば急に増えていた。
運動不足だけでは説明がつかない、そんな体の変化。
あなたにも、思い当たるところはありませんか?
もしかするとそれは、「隠れた心不全」のサインかもしれません。
特に、高血圧・貧血・腎機能の低下・心疾患のご経験がある方は、一度しっかりと検査してみることをおすすめします。
それでは、「心不全」とは何か――わかりやすく解説させていただきます。
🫀 こんな症状が増えていませんか?
- 階段を登ると息が切れるようになった
- 最近、顔や足のむくみが気になる
- 以前より昼間の疲れが取れにくい
- 夜中に息苦しくて目が覚める
- 横になると苦しくて、枕を高くしないと眠れない
- 急に体重が増えてきた(むくみのサイン)
- 「年齢のせいかな」と思って病院に行っていない
これらは心不全の初期症状としてよく見られます。
心不全は、心臓が「全身に血液を送る力」が弱まった状態です。
初期には「疲れやすい」だけでも、進行すると命にかかわることもあります。
📘 心不全とは?専門的なこともやさしく解説
心不全とは、「病名」ではなく心臓の機能が低下している状態を示す“病態”です。
さまざまな病気(高血圧、心筋梗塞、弁膜症、不整脈など)が原因で、心臓がポンプとしての役割を果たせなくなると、全身に血液をうまく送れなくなります。
心不全には大きく分けて以下の2タイプがあります:
- 収縮不全型(HFrEF):心筋が弱り、血液を送り出す力が低下した状態
- 拡張不全型(HFpEF):心筋の硬さが増して、血液をうまく受け取れなくなった状態(高齢者に多い)
最近では高齢化の影響で、特に後者のHFpEF(拡張不全型)が増えています。
これは心臓のポンプとしての出力は保たれているのに、息切れやむくみが出るという、気づかれにくいタイプです。
また、心不全は急に悪化する(急性増悪)ことがあり、早期の気づきと専門的な治療が大切です。
✅ 当院でできる対応
- 心電図・心臓エコー検査で心機能を評価
- 胸部レントゲン・採血(BNP検査など)で原因や重症度を判断
- 利尿薬や心保護薬などの内服処方
- 再発防止のための生活指導・食事相談
- 心臓リハビリテーションによる体力・生活の質の改善
💪 心臓リハビリの重要性
心不全は「診断して薬を出す」だけでは不十分です。
再入院を防ぐには、運動・食事・生活習慣の見直し=心臓リハビリが効果的です。
- 運動機能・体力の改善
- 再入院率の低下
- うつ・不安の軽減、生活の質の向上
当院では、理学療法士による指導のもと、安全な心臓リハビリを提供しています。
💬 循環器専門医からの一言
「年のせい」とあきらめてしまっていませんか?
まぶたや足のむくみ、ちょっとした息切れは、心不全の“はじまり”かもしれません。
心不全は、早期に気づいて対処することで進行を防げます。
生活の質の低下や入院を防ぐためにも、気になる変化があれば一度ご相談ください。
当院では、心臓リハビリにも力を入れています。
運動・栄養・服薬のサポートを通して、安心して暮らせる体づくりを応援します。
ご提案
“年のせい”と見過ごされやすい心不全
自覚症状がなくても
まぶたや足のむくみは、心不全の前兆かもしれません
心不全は寿命に直結する怖いご病気です
専門医として適切に判断し
健康寿命の延長のために
協力をさせてください
🔗 ご予約・ご相談はこちら
LINE公式アカウント: ![]()
お電話:0564-25-2511
ご予約なしでも直接ご来院いただけます
更新日:2025-09-27 場所:岡崎市真伝町 / 岡崎整形外科・循環器内科
本ページは一般向け解説です。個別の診療内容は来院時に医師がご説明します。
🔗 信頼できる外部リンク
補足の説明です(専門的な用語や内容を含みます)
心不全ガイドライン2025が改訂されました
心不全の患者さんは高齢化や生活習慣病の影響で年々増加しています。
2025年3月、日本循環器学会・日本心不全学会によって、心不全の診断と治療に関する最新のガイドラインが発表されました。
このページでは、主な改訂ポイントと、その内容をどのように診療に活かしていくかを詳しくご紹介します。
Ⅰ.疾患分類の見直しと診断の強化
- EFによる分類が明確化されました:
- HFrEF(EF≦40%)
- HFmrEF(EF 41–49%)
- HFpEF(EF≧50%)
それぞれに対応した推奨治療が示され、HFpEFにも積極的な治療介入が推奨されるようになりました。 - BNP・NT-proBNPの活用が推奨され、初期診断・治療方針決定・再入院リスク評価まで幅広く活用されます。
- HFpEFの診断には、「HFA-PEFF」や「H2FPEF」などの診断スコアを用いた形式的な判断が可能に。
◆患者さん向け解説:心不全は“心臓の元気がなくなる病気”ですが、症状が出にくいタイプ(HFpEF)もあります。
血圧管理や、血液検査(BNPなど)や心エコーなどで現状を評価し、少しでも心臓の障害を予防しましょう。
Ⅱ.薬物治療の標準化とエビデンス更新
- HFrEFに対して、以下の4剤併用療法が推奨されます:
- ACE阻害薬/ARB/ARNI(ネプリライシン阻害薬併用)
- β遮断薬(ビソプロロールなど)
- MRA(スピロノラクトン、エプレレノン、フィネレノン)
- SGLT2阻害薬(ダパグリフロジン、エンパグリフロジン)
- HFpEF患者にもSGLT2阻害薬の有効性が認められ、治療対象となりました。
◆患者さん向け解説:心不全の薬は4つをうまく組み合わせることで、心臓を保護し入院を防ぐことを目指します。
新しく使用できる薬剤が増えてきており、組み合わせや用量の調整が重要となります。
Ⅲ.非薬物・デバイス治療の進歩
- CRT(心室再同期療法)の対象がより厳密に。QRS幅やEFだけでなく、個々の症状や年齢も加味して判断されます。
- ICD(植込み型除細動器)は、心室性不整脈の予防だけでなく、予後改善にもつながる対象を精査。
◆患者さん向け解説:薬だけで治らないときは、ペースメーカーのような機械を使って心臓の働きを助ける治療もあります。
新たなディバイスも研究が進んでおり、将来的な活用が期待されます。
Ⅳ.AI・個別化医療の導入
- AIを用いたリスク予測:症状・検査・生活習慣をもとに、再入院リスクや治療反応を予測するAIモデルが紹介されました。
- トロポニン・ゲノム・画像データなどを組み合わせて、個々に合った治療を選ぶ「プレシジョンメディスン」の流れが加速しています。
◆患者さん向け解説:これからの医療は「あなたに合った治療」を選ぶ時代です。AIや最新検査を活かして、より安全で効率的な治療が将来的に期待されます。
Ⅴ.クリニック・在宅での対応の強化
- BNP測定を用いたフォローアップが推奨され、定期チェックによる早期再発防止が重要とされています。
- 遠隔モニタリング(血圧・体重・脈拍など)や、看護師・薬剤師との多職種連携が地域医療でも重視されるようになりました。
- 高齢者や在宅患者にも使いやすい、簡便な重症度スコア・診療フローが公開されています。
◆患者さん向け解説:病院に通えない方でも、日々の体調を見守りながら、重症化を防ぐ治療ができます。
ご家族や看護師さんと連携しながら、地域全体で支える時代になってきています。
早期診断(BNP/NT-proBNP)+SGLT2阻害薬を含む4剤併用+早期の評価と慎重なフォローアップで、
在宅重症化を防ぎ、生活の質向上をめざします。
このように、心不全治療は進歩を続けています。
当院でも、最新ガイドラインに沿った診療を実践しながら、地域の皆さまの健康をサポートしてまいります。