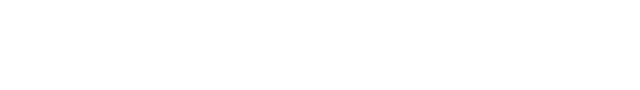心臓の健康を、もう一度。 安心して暮らすための “心臓リハビリ” New 2025/5/19
心臓の病気を経験された方の多くが
「また悪くなったらどうしよう」
と感じています
そんな不安を安心に変えるのが
「心臓リハビリ」です
私たちは、心臓の再発予防だけでなく
日常生活への自信を取り戻すための
お手伝いをしています
心臓リハビリテーションは
病気の再発予防、生活の質の向上を目指す
医療プログラムです
日常生活に少しずつ自信を取り戻し
明るい未来へと踏み出すための
サポートを行います
心臓リハビリとは?
心臓リハビリ(心リハ)は
心臓病や心臓等の手術を経験された方が
安心して社会復帰をし
また安定した生活を継続するために
運動療法・生活指導・心理的サポート
を組み合わせた
医療プログラムです
定期的な通院でリハビリを実施し
足の筋力の増強や全身の管理を通じて
日常生活での息切れなど
症状の軽減を目指します
心不全での再入院を予防し
健康寿命向上を期待します
代表的な対象疾患には
次のようなものがあります
狭心症・心筋梗塞
心不全
心臓手術後
(バイパス手術、弁膜症手術など)
カテーテル治療後
間欠性跛行
医師の管理のもと
安全に運動を行いながら
体力の回復・再発予防・服薬や食事の
アドバイスなどを受けられるのが特徴です
どんなことをするの?
-
安全な"有酸素"運動
(エルゴメーター、トレットミル、
ストレッチ、運動歩行、
無理のない筋力トレーニングなど)
-
心電図モニターでの体調管理
-
食事や生活習慣のアドバイス
- 内服治療の確認と調整
-
心理的不安へのサポート
- 定期的な筋力評価や体力測定
こんな方はぜひ
情報をチェックしてください
✅ 心臓の病気で入院・治療歴がある
✅ 運動に自信がない・疲れやすくなった
✅ 軽い運動や歩行でも息切れや動悸がある
✅ 再発が心配で不安がある
✅ 医師からリハビリをすすめられた
✅ 退院後、日常生活への復帰の不安
心臓リハビリは「運動をするだけ」ではありません。
薬だけに頼らず、再発を防ぎ、自信を持って日常を取り戻すための「総合的な回復支援」です。
「怖いから動かない」ではなく、
「安全に動くことで健康を守る」ことが大切です。
これらを、医師・理学療法士・看護師・管理栄養士など
多職種がチームでサポートします
医師からの一言
心臓病は“治ったら終わり”
ではありません
でも
今を維持し,再発させない工夫
症状を軽減する努力
はできます
心リハは、あなたの心臓を守る
お薬とその「次の治療」です
担当医師
循環器内科専門医
心臓リハビリテーション指導士
清水真也
ご不明な点、ご病気が対象かどうかなど
お気軽にご相談ください
ご予約・お問い合わせ
ご予約をご希望の方は
LINE公式アカウント![]() もしくは 0564-25-2511 まで
もしくは 0564-25-2511 まで
ご予約なしでも
直接ご来院いただけます
(診療時間を事前にご確認ください)
詳細ページ(外部リンク)
(日本心臓リハビリテーション学会)
(日本循環器学会)
当院での現状のご案内
現在、当院では心臓リハビリテーションの導入を準備中です
心不全・狭心症・手術後などの患者さんが
安心して地域で継続的なケアを受けられるよう、体制を整えています
しかし地域にはまだ、心臓リハに本格的に取り組む施設が多くはありません
今後の高齢化を見据えたとき、心不全パンデミックへの対応としても
この取り組みは重要だと感じています
現在、チーム体制の構築とともに、リハビリ専門の視点を取り入れるべく調整中です
まだ規模は小さいですが、熱意をもって始めたいと考えています
――もしこの内容に共感いただける理学療法士の先生がいらっしゃれば
ご質問やご相談など
ご質問フォームより直接ご連絡ください
地域医療の未来に共に関わっていただける方との出会いを、密かに期待しています
担当医師:心臓リハビリテーション指導士/リハ学会東海支部評議員 清水真也
以下,補足説明です
心臓の健康をもう一度 ~安心して暮らすための心臓リハビリテーション~
心臓の病気を経験された方へ。退院後、「また同じことが起きたらどうしよう…」と不安を感じていませんか?心臓リハビリテーション(以下、心臓リハビリ)は、そうした不安を和らげ、病気の再発予防と生活の質(QOL)の向上を目指す医療プログラムです。少しずつ日常生活に自信を取り戻し、明るい未来へ踏み出せるようサポートしていきます。岡崎市真伝町の岡崎整形外科・循環器内科でも心臓リハビリの導入準備を進めており、患者さんの安心な暮らしを地域で支える体制づくりに取り組んでいます。
心臓リハビリは主治医のもとで安心して進められます。医師やスタッフが寄り添い、不安を一つひとつ解消しながら進めていきます。
心臓リハビリとは?
心臓リハビリテーション(略して心リハ)とは、心臓病や心臓の手術を経験した患者さんが、安全に体力を回復し自信を取り戻して、快適な家庭生活や社会生活に復帰するとともに、病気の再発や再入院を防止することを目指して行う包括的な活動プログラムのことですjacr.jp。運動療法だけでなく、食事指導や生活習慣の指導、心理的サポートなどを組み合わせ、多職種チーム(医師、理学療法士、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床心理士 等)が患者さん一人ひとりの状態に応じたプログラムを提案・実施しますjacr.jp。
心臓リハビリは主に退院後に定期的な通院で行います。医師の管理のもと、血圧や心電図など体調をモニターしながら安全に運動を継続し、徐々に足腰の筋力アップや全身持久力の向上を図ります。その結果、日常生活で感じていた息切れなどの症状が軽減し、心不全の再入院を予防して健康寿命の延伸も期待できます。
対象となる方は、代表的なものでは次のような心疾患の患者さんです:
-
狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患
-
心不全(慢性心不全)
-
心臓手術後(冠動脈バイパス術、弁膜症手術など)
-
カテーテル治療後(経皮的冠動脈形成術など) など
これらの病気では、発作や手術を経て心臓の機能が低下したり、安静療法により筋力や持久力が落ちていることが少なくありません。「退院直後は体を動かすのが怖い」「どの程度動いて良いかわからない」といった不安の声もよく聞かれます。しかし心臓リハビリでは、専門スタッフのもとで適切な運動処方が行われるため、無理なく安全に身体を動かすことができます。さらに動脈硬化の進行を防ぐための食事指導や禁煙指導、服薬管理のサポートも含まれており、患者さんの不安を包括的にケアします。
心不全・心筋梗塞後・手術後の患者さんにおいては、心臓リハビリを受けることで次のような効果が報告されています:
- 心血管イベントの再発リスク低下
- 再入院率の大幅な減少
- 死亡率の低下(長期的には有意差あり)
- 運動耐容能の改善(6分間歩行距離の延伸など)
- 生活の質(QOL)の向上
- うつ・不安症状の緩和
- 社会復帰率の改善
心臓リハビリでは何をするの?
心臓リハビリのプログラム内容は多岐にわたりますが、主な柱は次のとおりです:
-
有酸素運動トレーニング: 医師の指示のもと、エルゴメーター(自転車こぎ)やトレッドミル(ルームランナー)での歩行運動、ストレッチや軽い筋力トレーニングなどを行います。強度や時間は一人ひとりの体力に合わせ設定され、無理のない範囲で心肺持久力を向上させます。
-
モニタリングによる安全管理: リハビリ中は心電図や血圧、酸素飽和度などを監視し、症状の変化にすぐ対応できる体制を整えています。急な血圧上昇や不整脈の兆候がないか確認し、安全第一でプログラムを実施します。
-
生活指導・栄養指導: 血圧やコレステロール管理、糖尿病対策のための食事療法のアドバイスや減塩指導を行います。また禁煙支援や服薬アドヒアランスの確認など、再発予防のための生活習慣改善をサポートします。
-
心理社会的サポート: 心臓病を経験した後は、「また発作が起きるのでは」という不安や落ち込みを抱える患者さんも少なくありません。心臓リハビリでは心理士等によるカウンセリングや不安軽減のケアも行い、メンタル面でも患者さんを支えます。
リハビリでは看護師や理学療法士が寄り添い、運動や生活面の指導を行います。ただ運動するだけでなく、日々の食事内容やお薬の管理、気持ちの落ち込みへの対応まで、総合的にサポートします。
以上のように、**心臓リハビリは「運動だけではない」**点が大きな特徴です。医師・理学療法士・看護師・管理栄養士・臨床心理士といった専門スタッフがチームとなって、患者さんを全人的に支援します。心臓病は身体面だけでなく精神面や生活習慣にも影響を及ぼすため、こうした多角的アプローチによって再発リスクを下げ、安心して暮らせる日常を取り戻すことが目指されます。
心臓リハビリを始めるには
主治医から心臓リハビリを勧められた方や、「体力に自信がなくなった」「また入院するのではと心配だ」という方は、ぜひ一度ご相談ください。特に以下のような方は心臓リハビリについて情報をチェックしてみましょう。
-
心臓の病気で入院や治療を受けたことがある
-
最近、動くと疲れやすくなり運動に不安を感じる
-
心臓病の再発が心配で日常生活でも緊張や不安がある
-
医師からリハビリを勧められたが、どうすれば良いかわからない
-
退院後の生活復帰に不安が強い
心臓リハビリは保険診療のもと、医師の指示に基づいて実施されます。当院でも現在、心臓リハビリテーションの提供開始に向けチーム体制の構築を進めております。まだ地域では心臓リハビリに本格的に取り組む施設は多くありませんが、高齢化による“心不全パンデミック”に備えて地域で継続的なリハビリを受けられる体制づくりは重要だと感じています。私たちも規模は小さいながら熱意を持ってこの取り組みを始め、患者さんの安心な生活を末長く支えていきたいと考えています。
医師からのひとこと: 心臓病は「治ったら終わり」ではありません。でも、今の状態を維持し、再発させない工夫や症状を軽減する努力はできます。心臓リハビリは、あなたの心臓を守るお薬とその「次の治療」です。(循環器内科医・心臓リハビリテーション指導士 清水 真也)
エビデンスで見る心臓リハビリの効果
心臓リハビリテーションの有用性は、国内外の多数の研究やガイドラインで強調されています。包括的心臓リハによる継続的な管理は、患者の予後を改善しQOLを高めるだけでなく、再入院の減少や寿命の延長にも寄与します。以下、最新エビデンスとガイドラインの内容を概観します。
再発予防・予後改善のエビデンス
心臓リハビリ参加の有無で患者の予後に大きな差が出ることが、統計的にも示されています。例えば、虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)の患者さんでは、心臓リハビリを行うことで心血管死亡率が26%低下し、入院のリスクが18%低下したとの報告があります。また心不全患者さんでは、リハビリ非参加の場合に比べてあらゆる原因の入院が25%減少し、特に心不全による入院は39%も減少したとのデータも得られています。このように、適切な運動療法を中心とした心臓リハビリは、カテーテル治療や薬物療法に劣らない重要な治療法であり、再発や再入院を防ぐ効果が期待できると指摘されています。
心理面への効果も見逃せません。運動を継続し汗を流すことで不安や抑うつ症状が軽減し、生活に対する前向きな意欲が湧くケースも多く報告されていますportailvasculaire.fr。実際、欧州心臓病学会(ESC)のガイドラインでも、「心臓リハビリテーションはうつや不安の症状を減少させ、患者の生活の質を改善する」ことが述べられていますportailvasculaire.fr。
心臓リハビリの効果について医療スタッフ間で情報共有する様子のイメージイラスト。エビデンスに基づき、多職種チームでリハビリ計画を立案します。
ガイドライン(国内外)での位置づけ
日本循環器学会や日本心臓リハビリテーション学会の公式資料でも、心臓リハビリの重要性は繰り返し強調されています。日本循環器学会の解説によれば、適切な運動処方に基づく心臓リハビリテーションは患者さんの生活の質を改善し、入院を減らすことが分かっているとされていますj-circ.or.jp。また米国心臓協会(AHA)や米国大学心臓病学会(ACC)も、心臓リハビリが心血管疾患患者の死亡率を下げ、QOLを向上させることをエビデンスに基づき報告し、ガイドラインの中で強く推奨していますportailvasculaire.fr。
欧州心臓病学会(ESC)の**予防指針(2021年改訂版)**では、心臓リハビリテーション(包括的な二次予防プログラム)について次のように記載されていますportailvasculaire.frportailvasculaire.fr。
-
「包括的心臓リハビリや予防プログラムは、心血管イベント後の患者において、心血管疾患による入院、心筋梗塞、心血管死を減少させ、一部のプログラムでは全死亡率も低下させる。また抑うつ・不安症状を軽減させる可能性がある。」portailvasculaire.fr
-
「運動を基盤とした心臓リハビリ(EBCR)は、全死亡率の改善、入院の減少、運動耐容能および生活の質の向上をもたらすことが示されている。心臓リハは一般に費用対効果も高い。」portailvasculaire.fr
こうしたエビデンスを背景に、国内外のガイドラインでは心臓リハビリの実施が強く推奨されています。例えば慢性心不全に対するガイドラインでは、安定期の心不全患者に対して医療監督下での包括的心臓リハビリを行うよう勧告されています(クラスⅠ, エビデンスレベルA)。日本でも、2025年の心不全診療ガイドライン改訂版においてリハビリテーションの重要性が明記され、急性期から維持期・在宅期まで切れ目なくリハビリ介入を行う意義が強調されています。入院早期からの理学療法や運動療法が患者の運動機能や認知機能、退院後QOLに良い影響を与えることが確認されており、エビデンスに基づくリハビリ介入が予後改善につながると期待されています。
代表的な研究例:FLAGSHIPスタディ
心臓リハビリの効果を示す個別の臨床研究も数多く報告されています。その一つが日本で行われた大規模研究**「FLAGSHIP」**です(FLAGSHIP: Frailty in Heart Failure Study)。以下にその代表的な論文の一例を紹介します。
-
Prognostic effects of cardiac rehabilitation in heart failure patients classified according to physical frailty: A propensity score–matched analysis of a nationwide prospective cohort study (FLAGSHIP)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov DOI: 10.1016/j.ijcrp.2023.200177 – 2023年に発表されたこの研究は、入院治療を受けた心不全患者を対象に心臓リハビリの予後への影響を検討したものです。2年間の追跡期間で、退院後3か月以内に定期的な心臓リハビリ(週1回以上)を行った群と行わなかった群を比較したところ、リハビリ実施群では心不全による再入院の発生率が有意に低下しましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。この傾向は患者を非フレイル群とフレイル(虚弱)群に分けた両方で認められ、フレイルな高齢患者においても心臓リハビリ参加が再入院リスクの低減につながることが示されています。この研究は、日本全国の多数の医療機関が参加した前向きコホートの解析であり、エビデンスの質としても貴重なものと思います。
地域連携と今後の課題
心臓リハビリテーションの効果を最大限に引き出すには、長期にわたって継続することが重要です。入院中の急性期リハだけでなく、退院後の維持期・在宅期においてもリハビリを切れ目なく提供する体制づくりが求められます。そのためには地域医療連携の充実が不可欠です。地域の病院やクリニック、施設が協力し合い、患者さんが定期的に心臓リハビリ施設を受診し続けられるような長期プログラムの構築が必要だと言われています。
しかし現状では、心臓リハビリの普及にはいくつかの課題があります。特に高齢の心臓病患者では、体力的な問題や併存疾患のために外来リハビリへの通院が困難なケースが少なくありません。ある報告では、「高齢患者が外来心臓リハビリに通えない最大の理由は歩行障害である」ことが指摘されています。実際に要介護レベルの高い心不全患者ほど外来リハビリ参加率が低下する傾向も報告されており、通院できない患者へのアプローチが課題です。このような背景から、近年では在宅心臓リハビリ(訪問リハ)や遠隔指導(オンライン心リハ)といった新しい取り組みも始まっています。在宅型心臓リハでは、リハビリ専門職が患者宅を訪問してリハを行ったり、自宅でできる運動プログラムを処方して地域全体で患者を支える試みがなされています。
心臓リハビリの重要性については医療政策の面でも認識が高まっています。厚生労働省の研究班は循環器病の維持期リハビリ有効性検証プロジェクトを立ち上げ、地域のかかりつけ医とも連携した長期心臓リハビリ体制のガイドブックを作成するなどの取り組みを進めていますcardiac-rehab.jp。地域包括ケアの中に心臓リハビリを位置づけ、「治療後も患者さんを地域で支える」しくみを作ることが、超高齢社会における心不全パンデミックへの対策として急務と言えるでしょう。
岡崎整形外科・循環器内科でも現在、心臓リハビリテーションの提供開始に向けて準備を進めています。当院のようなクリニックでリハビリを受け、その後も地域の医療機関同士が連携して患者さんをフォローしていくことで、入院と在宅の橋渡しをスムーズにし再入院を防ぐことが可能になります。私たちも地域の病院・施設と協力しながら、患者さんが**「いつでも、どこでも」リハビリを続けられる環境**を整えていきたいと考えています。それがひいては地域全体の医療水準の向上と、患者さんの人生の質の向上につながると信じています。
※参考文献(References):
-
【22】日本循環器学会 一般向け解説「しんふぜん 心不全」j-circ.or.jp
-
【27】厚生労働省「虚血性心疾患の運動療法について」資料mhlw.go.jp
-
【41】Adachi T, et al. FLAGSHIP (Int J Cardiol Cardiovasc Risk Prev. 2023)pubmed.ncbi.nlm.nih.govpubmed.ncbi.nlm.nih.gov
-
【46】ESC 2021年予防ガイドラインportailvasculaire.frportailvasculaire.fr